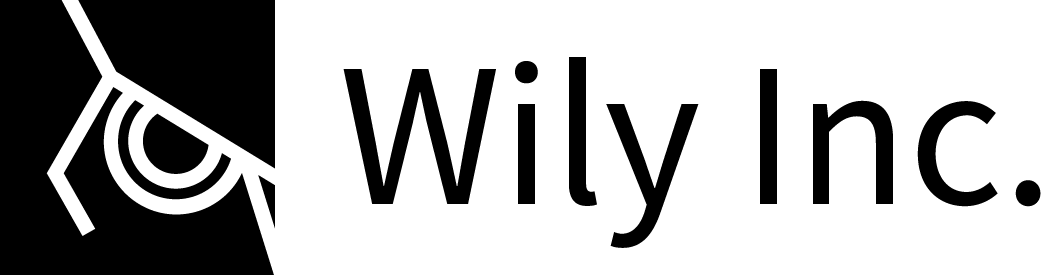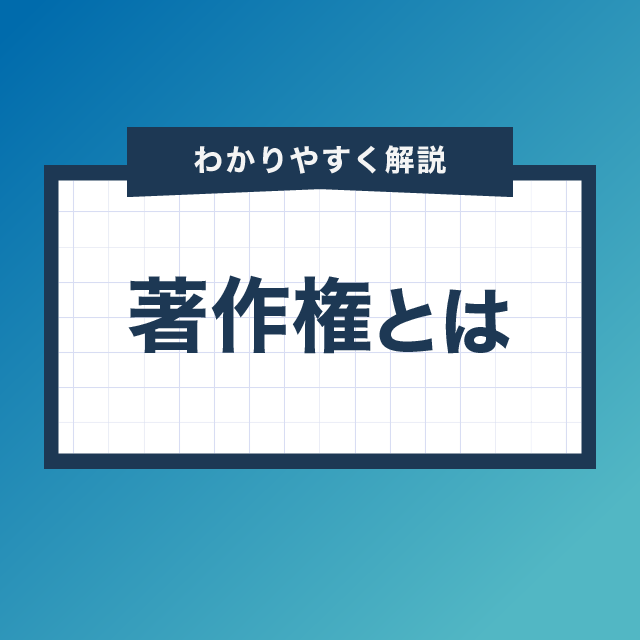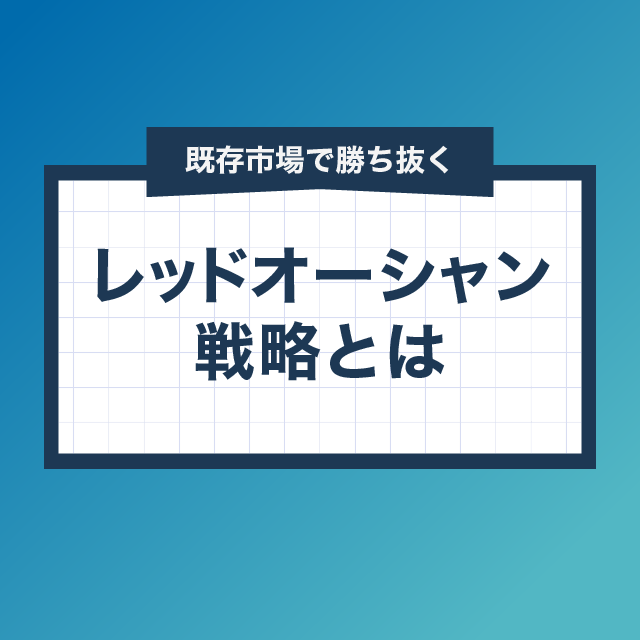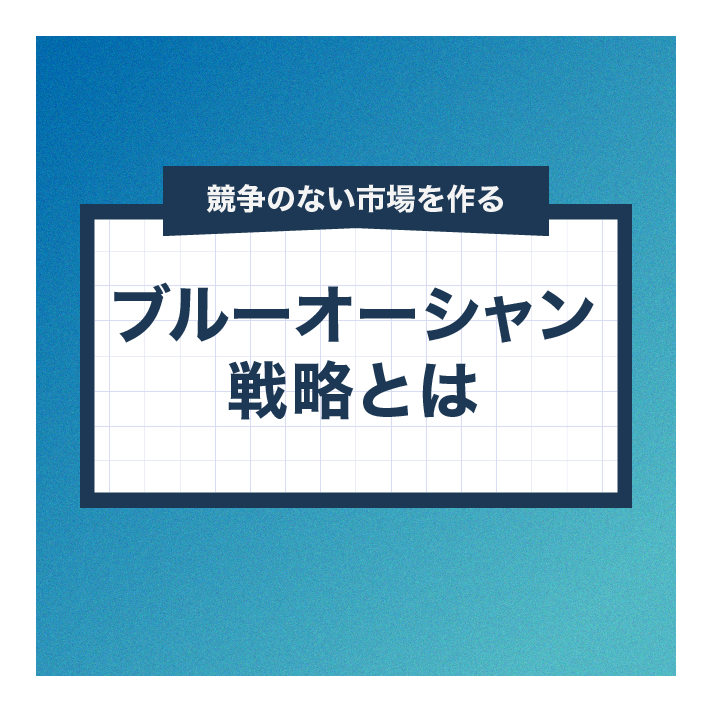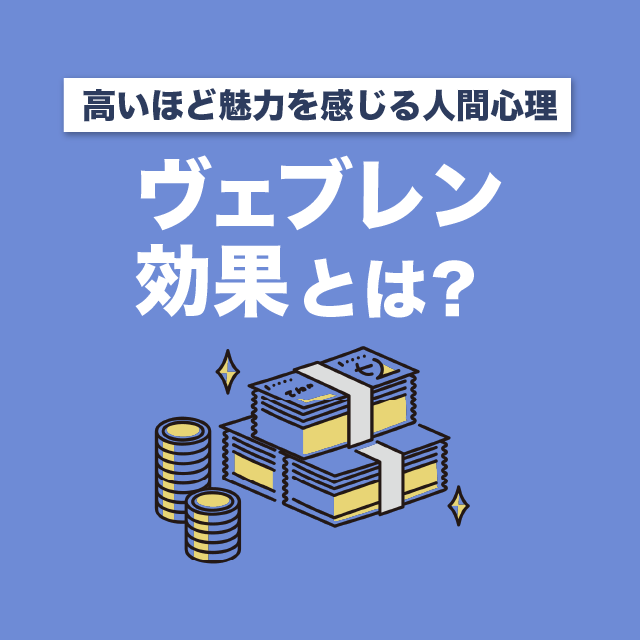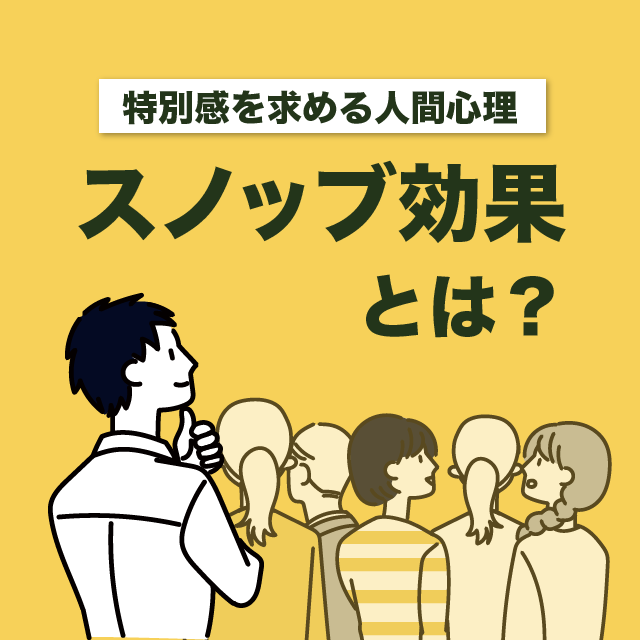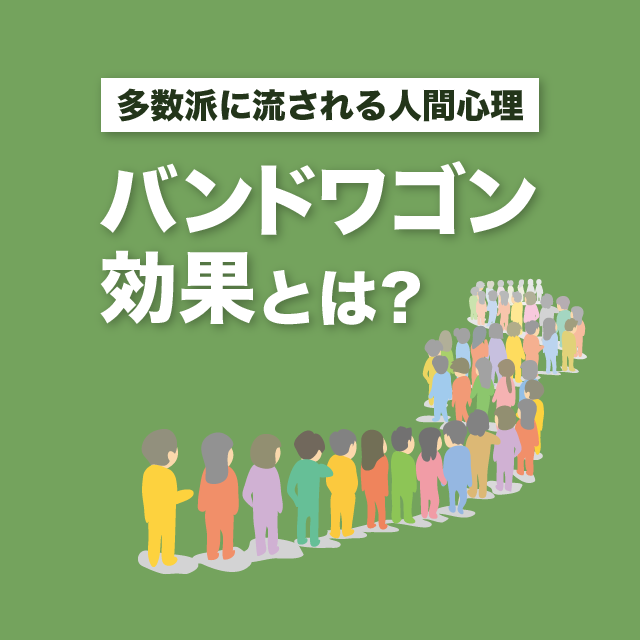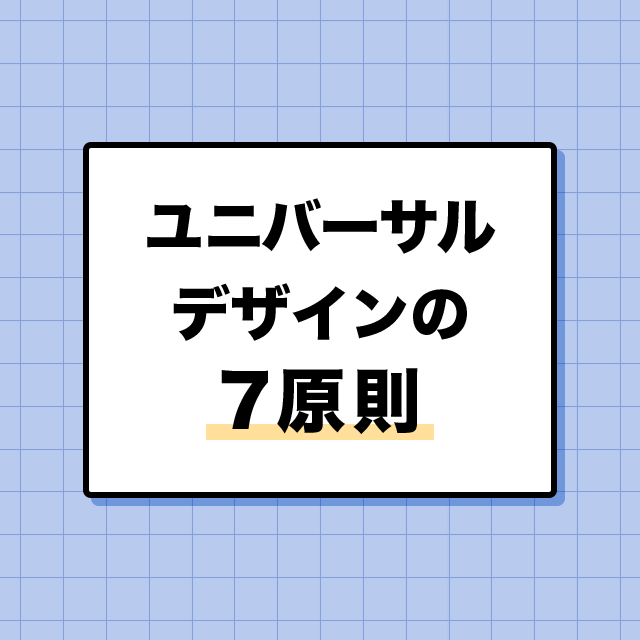フィッツの法則とは
フィッツの法則は、1954年にポール・フィッツ(アメリカの心理学者)によって提唱された、人間の動作とターゲットに到達するまでの時間の関係を示す法則です。この法則は、特にユーザーインターフェース(UI)やプロダクトデザイン、工業設計の分野で広く応用されており、「どのくらい早く・正確にある目標に到達できるか」を予測するために使われます。
フィッツの法則の基本式
フィッツの法則は以下の数式で表されます。
MT = a + b × log₂(2D/W)
ここで、
- MT は目標に到達するまでの運動時間(Movement Time)
- D は目標までの距離(Distance)
- W は目標の幅(Width)
- a, b は経験的に求められる定数
この式の意味は、「目標が遠くて小さいほど、その目標に到達するのは難しく、時間がかかる」ということです。逆に、目標が近くて大きければ、すばやく簡単にそこに到達できるという考え方です。
日常的な例で見るフィッツの法則
1. スマートフォンの操作
スマートフォンの画面で、「戻る」ボタンや「閉じる」ボタンが小さく画面の端にある場合、押しづらく感じることがあります。これは「目標が小さく、距離もある」ため、フィッツの法則によると操作に時間がかかり、誤操作の可能性も高くなることを意味します。そのため、最近のデザインでは「スワイプで戻る」など、指の届きやすいジェスチャーが導入されています。
2. パソコンの操作とカーソル
マウス操作においてもフィッツの法則は適用されます。例えば、画面の四隅はカーソルが自動的に止まり、すばやくアクセスできる理想的な場所です。Windowsのスタートメニューが左下、macOSのDockが下部中央に配置されているのも、この法則に基づいています。
3. エレベーターのボタン
エレベーターの「開く」「閉じる」ボタンが小さすぎたり、壁の高い位置にあると押しにくく感じるのは、目標までの距離が遠く、面積が小さいからです。よく利用されるボタンは、手が届きやすい位置に大きく配置することで、誰でもすぐに操作できるようになります。
4. ATMや券売機のタッチパネル
公共機関の券売機やATMの画面では、タッチするボタンが大きく、間隔も広く設計されています。これは高齢者や子どもでも簡単に操作できるよう、目標を「近く・大きく」しているためであり、フィッツの法則の実践的な応用例です。
デザインへの応用と工夫
1.ナビゲーションボタンのサイズを大きくする
ユーザーがよく使うボタンは視認性を高め、クリックしやすくすることで操作性を向上させます。
2.指が届きやすい位置に配置する
スマホの下部中央に重要な操作ボタンを置くことで、片手でも使いやすくなります。
3.操作頻度と配置の関係を最適化する
使用頻度の高い要素は、距離を短く・サイズを大きくしておくことで、操作の効率が格段に上がります。
まとめ
フィッツの法則は、「目標までの距離」と「目標の大きさ」が人間の動作速度にどう影響するかを示す、非常に実用的な法則です。スマホ、パソコン、公共設備など、私たちの日常のあらゆる場面に応用されており、快適な操作性やアクセシビリティを支える重要な設計原則です。この法則を理解することで、単に「使える」だけでなく、「直感的に気持ちよく使える」デザインの設計が可能になります。