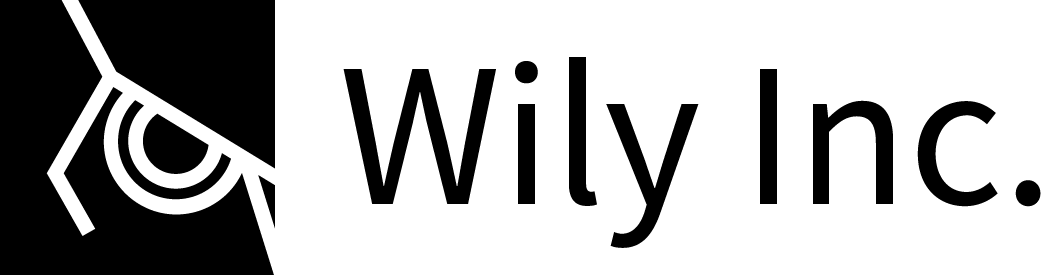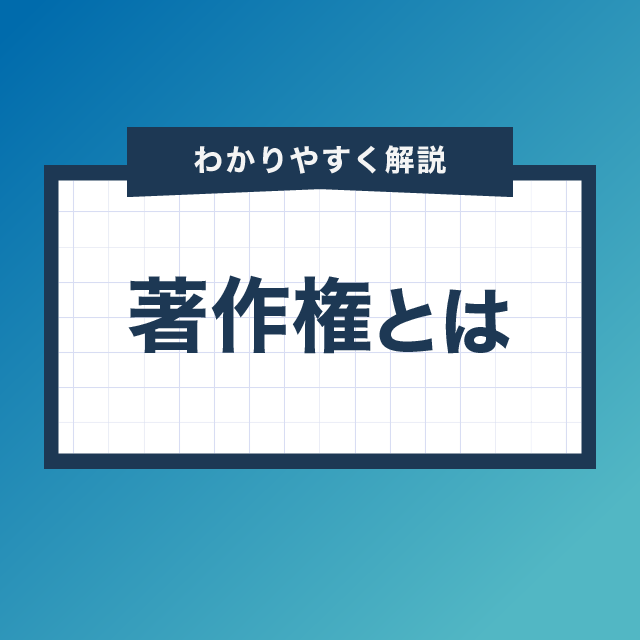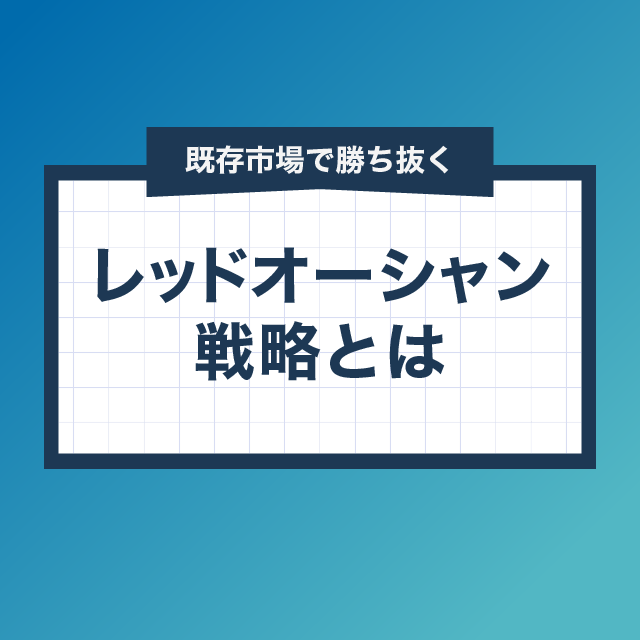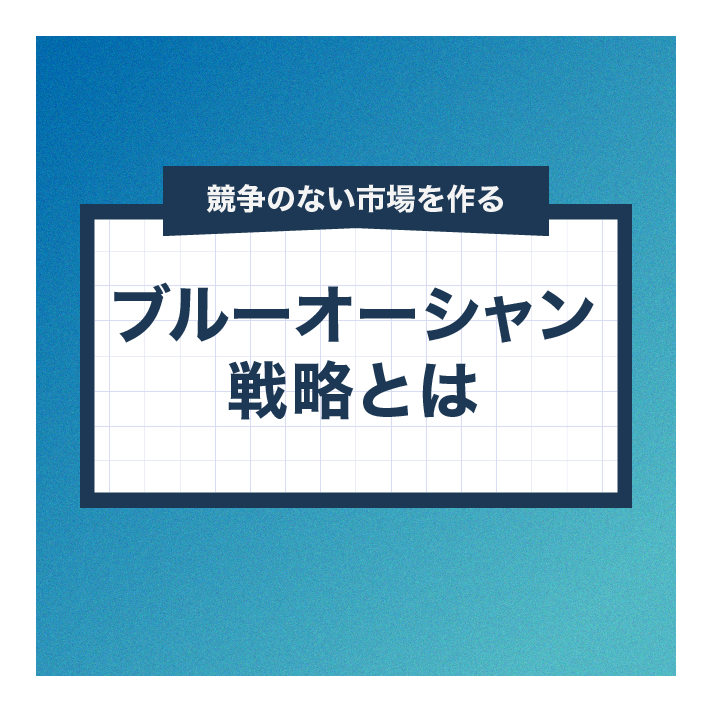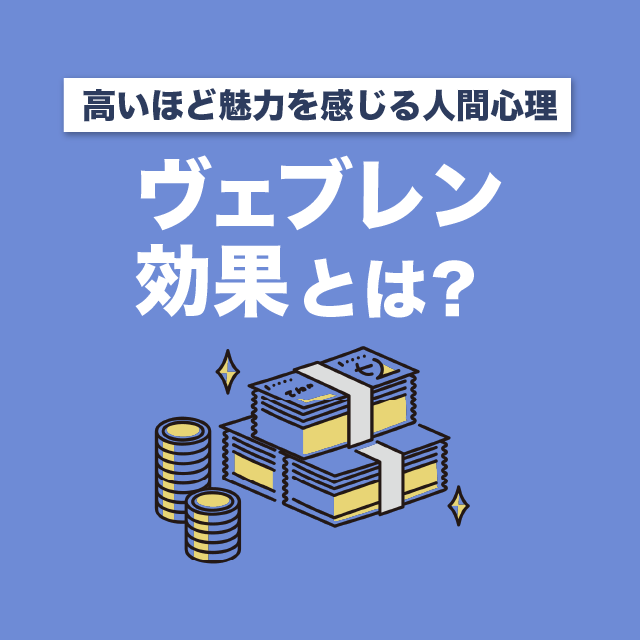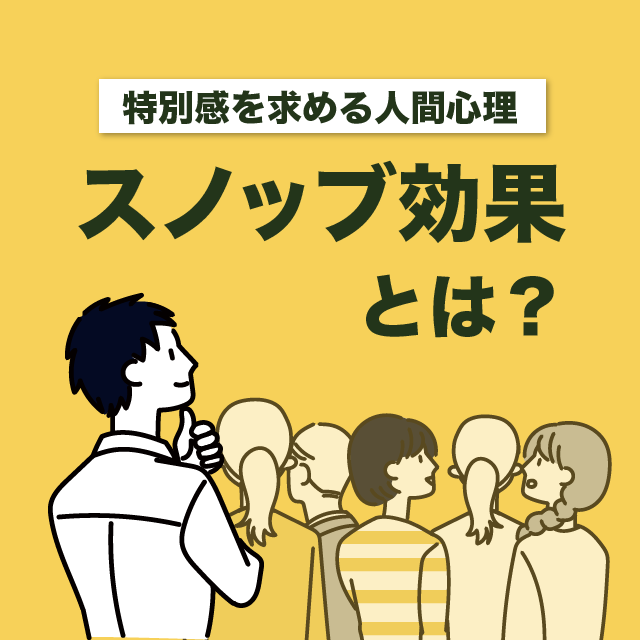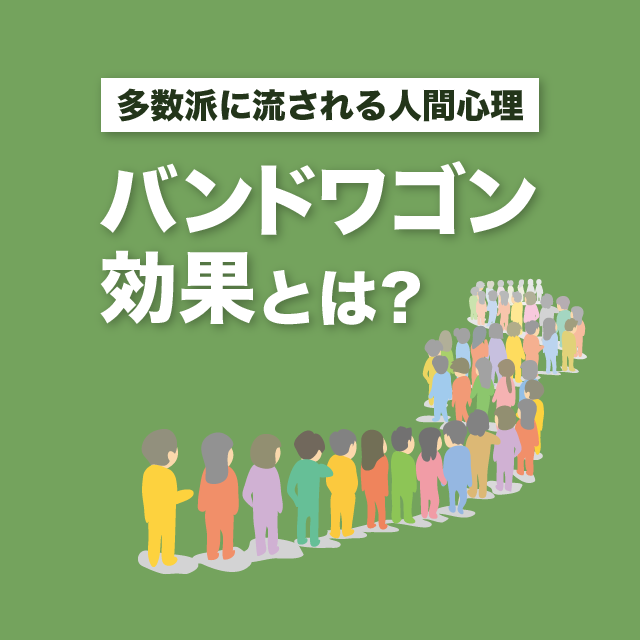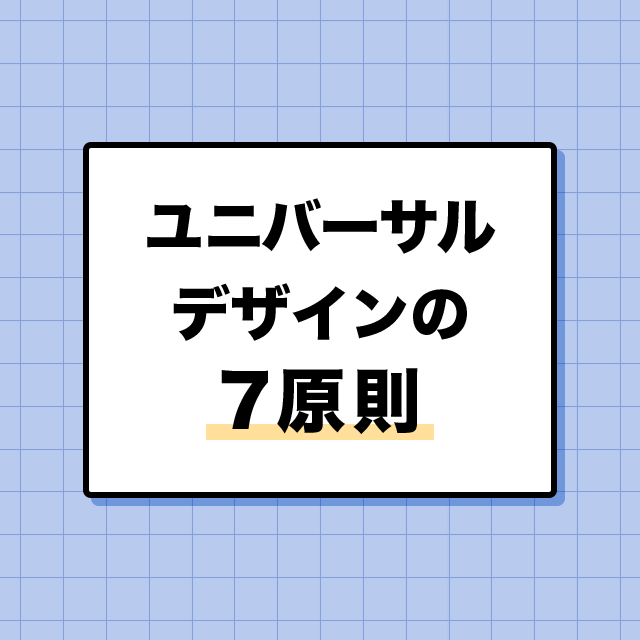ザイオンス効果とは
ザイオンス効果とは、人がある対象に繰り返し接することで、その対象に対する好感や親しみが自然と高まる心理現象のことです。ポーランド出身のアメリカで活動した心理学者ロバート・ザイオンスによって提唱されました。別名で「単純接触効果」とも呼ばれます。
たとえば、初対面の人に警戒心があったとしても、何度も顔を合わせているうちになんとなく親しみを感じるようになっていたり、CMで流れている曲を何度も聴くうちに好きになっていたりすることはザイオンス効果の一例と言えます。
ザイオンス効果のビジネス活用例
広告やSNS・メールマガジンでの発信
顧客との接点を定期的に持つことで、ブランド認知や信頼感を育てることができます。同じ商品名を何度もテレビCMやWeb広告、SNSで目にしていると、買ったことがなくても「良さそう」「聞いたことある」と感じて選ぶ可能性が高くなります。
営業担当者の定期訪問や連絡
一度の提案で成果を出すよりも、何度か訪問やフォローアップを重ねることで、この人なら信頼できそうという印象を与え、関係構築がスムーズになります。ただし、しつこすぎる接触は逆効果になるため、頻度やタイミングの調整が重要です。
展示会やセミナーでの継続的な出展
業界内のイベントや展示会に繰り返し出展することで、「よく見かける企業」として認識され、信頼感や安心感を与えることができます。特に初対面の企業と取引する際、過去に何度も名前を見聞きしていることがプラスに働くことがあります。
ブランド要素の一貫した使用
企業ロゴ、スローガン、カラーパレットなどをブレずに継続的に使うことも、ザイオンス効果が得られます。繰り返し同じビジュアルやメッセージを見せることで、企業や商品が記憶に定着しやすくなり、競合との差別化にもつながります。
ザイオンス効果の注意点
ザイオンス効果は繰り返せば必ず好感が生まれるというものではありません。以下のような条件が揃っていない場合、逆効果になることもあります。
初期印象が極端に悪い場合
すでに対象に対して悪い印象を持っている人に対してはザイオンス効果は発揮しづらくなります。悪い印象を持っている人に対して何度も接触してしまうとさらに不快感を与えてしまう可能性があります。ザイオンス効果は良い印象も悪い印象も持ってない人や少しでも好感を持っている人に対して効果を発揮します。
接触頻度が不自然に高すぎる場合
過剰露出は「押しつけがましい」「うるさい」と感じさせてしまうことがあります。7回の接触で購買意欲が高まるというセブンヒッツ理論を参考にすると、接触回数の目安は7〜10回が望ましいと考えられます。
質より量に偏った場合
ザイオンス効果を得るにはまずは接触回数を増やすことが大切ですが、回数ばかりを重視して質が伴わないと逆効果になる可能性があります。同じ文章のメールや対象者の興味がない情報を頻繁に送るとかえって不快感を与えてしまいます。
まとめ
ザイオンス効果は、接する回数が増えるほど、好感度が上がるという心理法則です。広告やブランディング、コミュニケーションなど、様々な場面で効果を発揮します。ただし、初期印象や接触の質を無視して数だけを増やしても効果は得られにくいため、適切な設計と継続的な配慮が求められます。