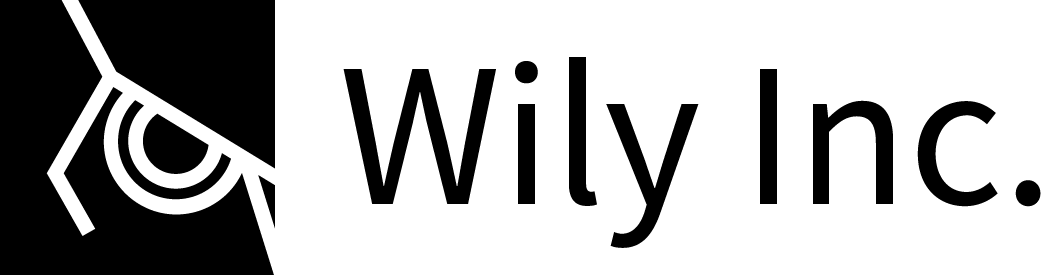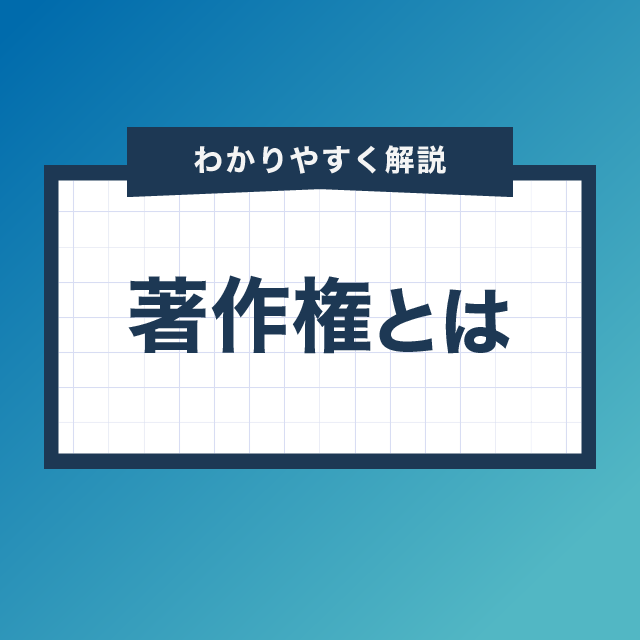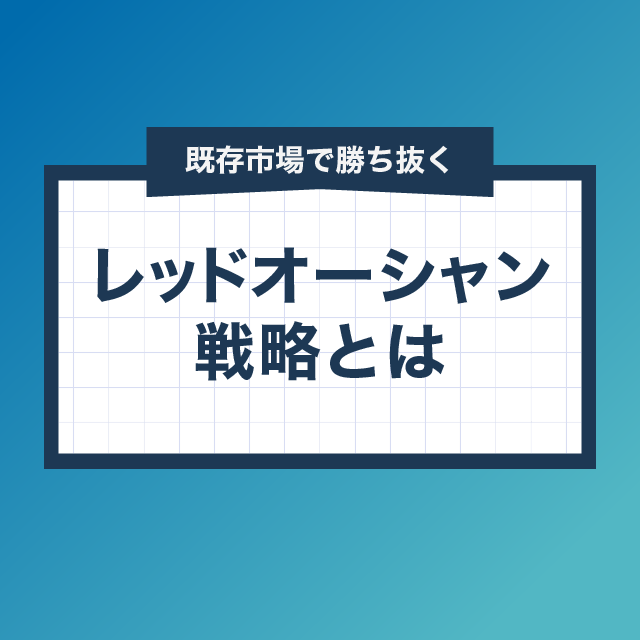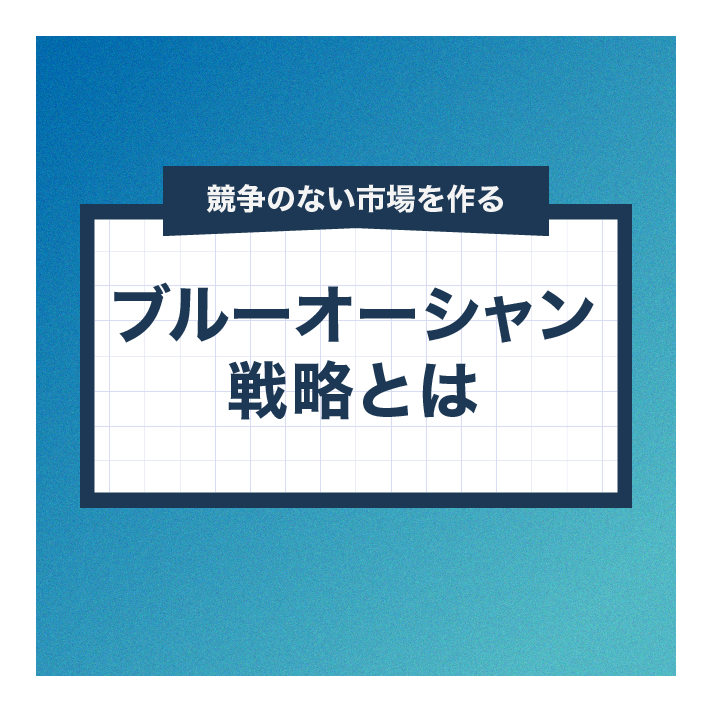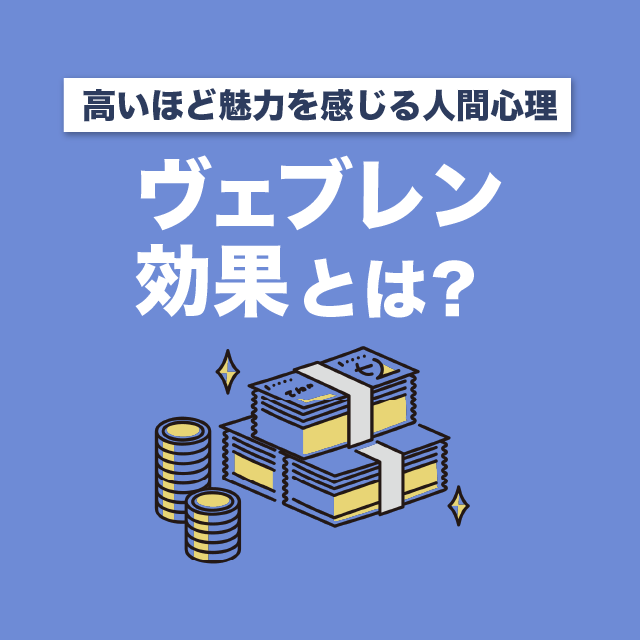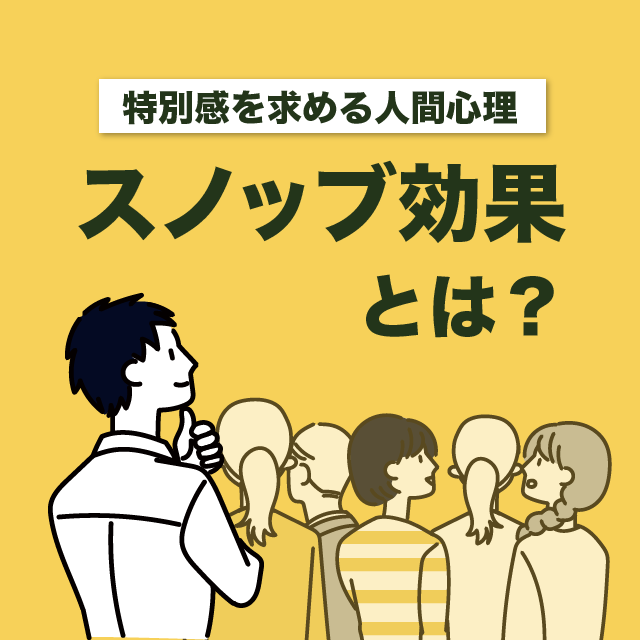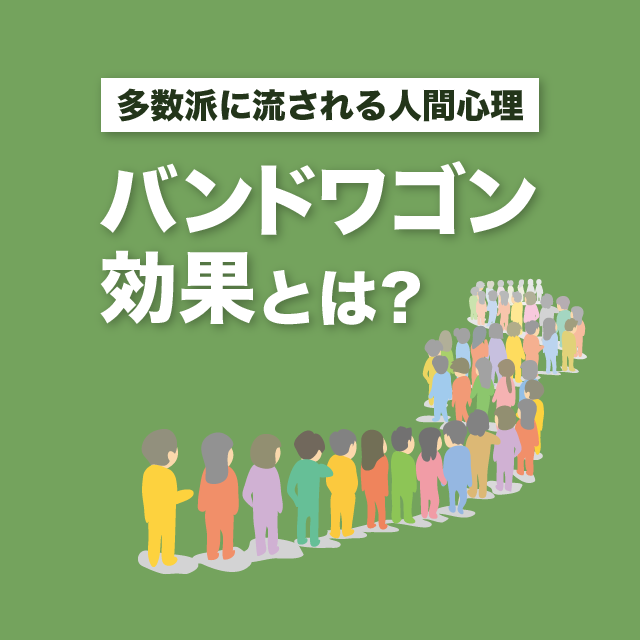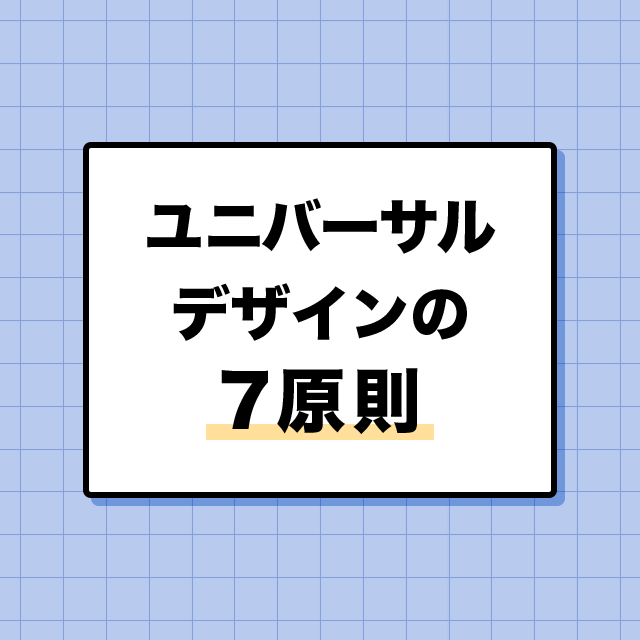スリーヒッツ理論とセブンヒッツ理論は、広告やマーケティング分野において人が何度の接触を経て商品やブランドに好感や関心を持つようになるかを示した理論です。どちらも接触の回数が増えるほど、印象や記憶、好意が形成されやすいというザイオンス効果(単純接触効果)をベースにした考え方ですが、それぞれの段階や目的に応じて活用の仕方が異なります。
スリーヒッツ理論
スリーヒッツ理論とは
スリーヒッツ理論は、消費者が商品やサービスを認知するまでには、最低3回の接触が必要であるという考え方です。これは比較的短期間のプロモーションやキャンペーンで効果を狙う時に有効です。
スリーヒッツ理論の3ステップ
1回目の接触:存在を知る
バナー広告やチラシで初めて商品を目にする段階ですが、商品についての理解や行動にはまだ結びつきません。
2回目の接触:記憶に残る
SNSや別の広告で同じ商品を見て「見たことがある」と感じる段階です。
3回目の接触:関心を持つ
商品サイトにアクセスして詳しく調べたり、口コミを見たり行動に移す段階です。
セブンヒッツ理論
セブンヒッツ理論とは
一方、セブンヒッツ理論は、消費者が最終的に購買や利用を決断するには、最低7回程度の接触が必要であるとされる考え方です。購買行動モデルのAIDMAやAISASとともに扱われます。
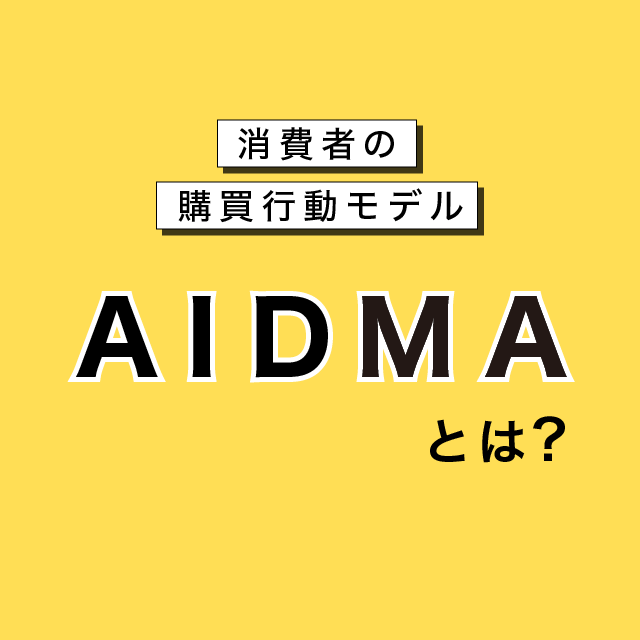
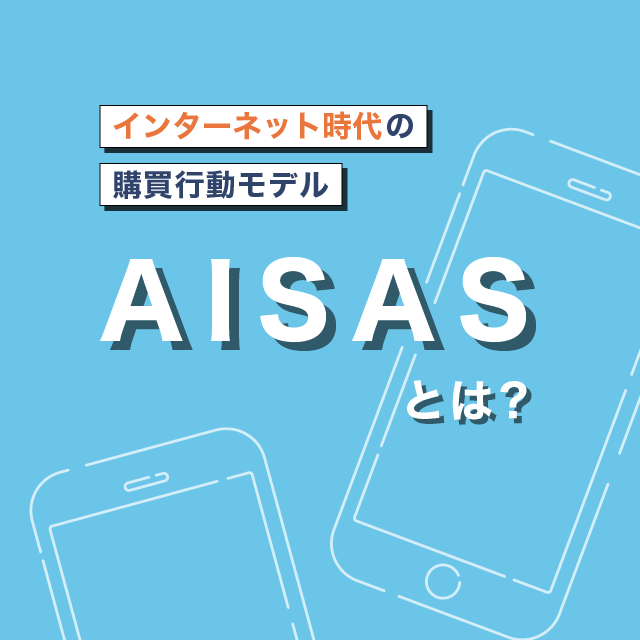
ブランドへの信頼や安心感、商品の理解を深めるためには、単なる接触ではなく、継続的かつ多面的な接触であることが重要です。
この理論は、中長期的なブランド構築やファン形成を目的としたマーケティング施策に有効です。特に高価格帯商品や継続購入が前提のサービス(例:車、保険、教育など)では、複数回の接触によって心理的ハードルを下げる必要があります。
活用方法
広告戦略の設計
短期的なリーチ拡大を狙う場合はスリーヒッツ理論に基づいて、広告を3回以上目にする機会を作ります。一方、ブランド認知やロイヤルティを育てたいときは、セブンヒッツ理論を意識して多様なチャネルと接点を設計します。
顧客接点の強化
フォロー、いいね、メルマガ、リターゲティング広告などを通じて、自然に複数回の接触が生まれる仕組みを作ることで、ユーザーの記憶と興味を深められます。
購入プロセスの分析
顧客が何回目の接触で購買に至ったかを分析することで、接触設計や広告費の最適化にもつながります。
まとめ
スリーヒッツ理論とセブンヒッツ理論は、どちらも人は繰り返し接することで好感を持ちやすくなるという心理原則に基づいたマーケティング理論です。違いは、接触回数と目的の深さにあり、商品・サービスの性質や広告戦略のスパンに応じて、使い分けることが重要です。