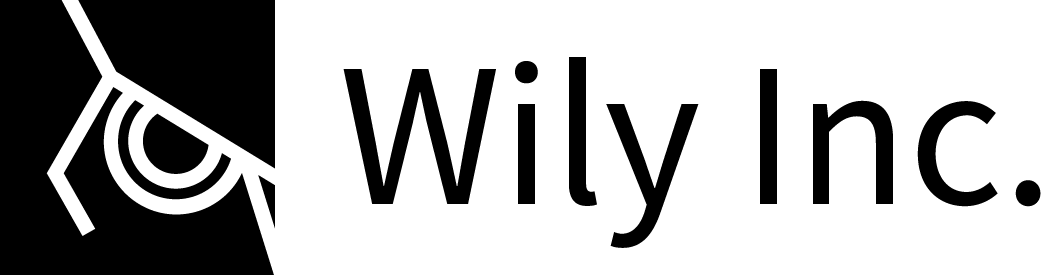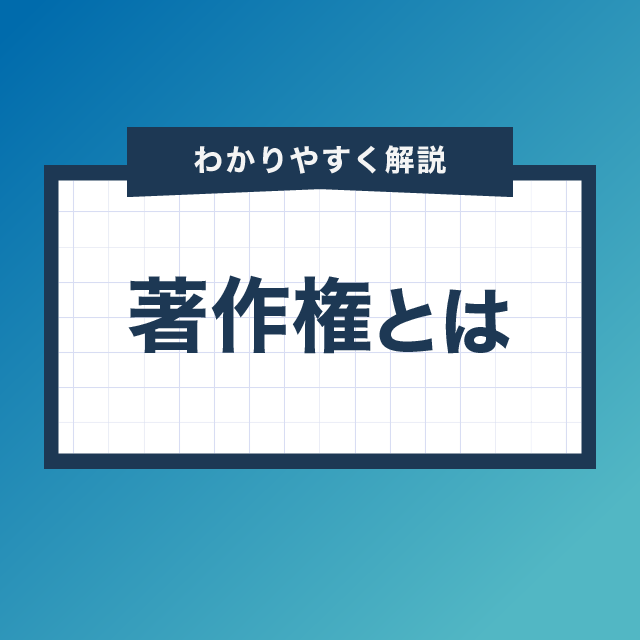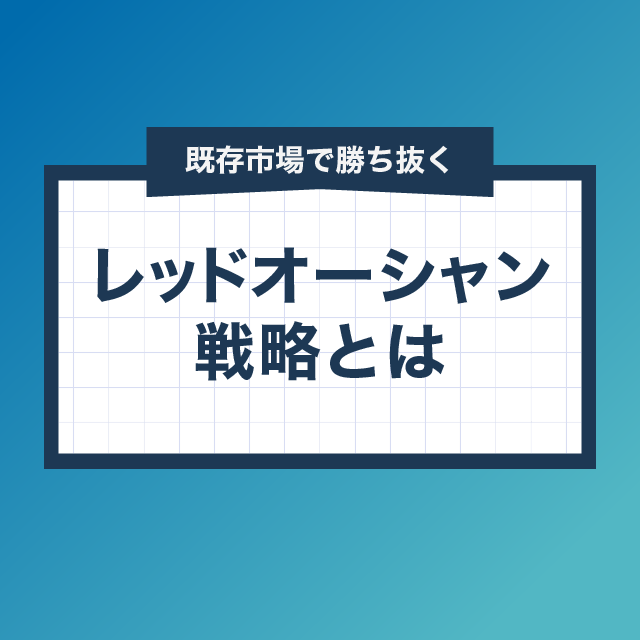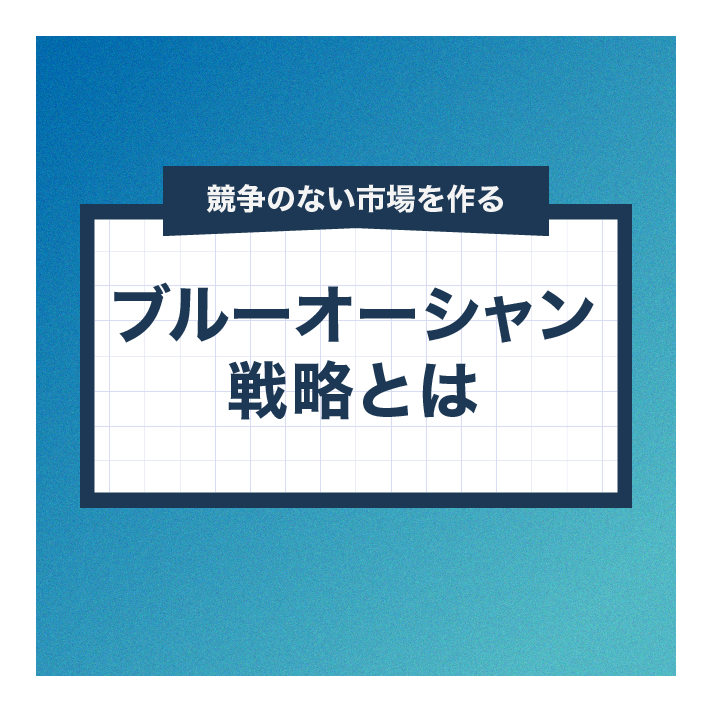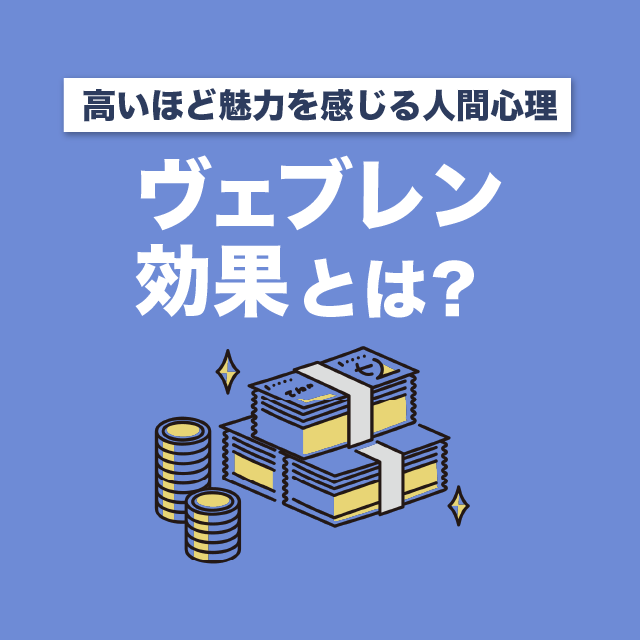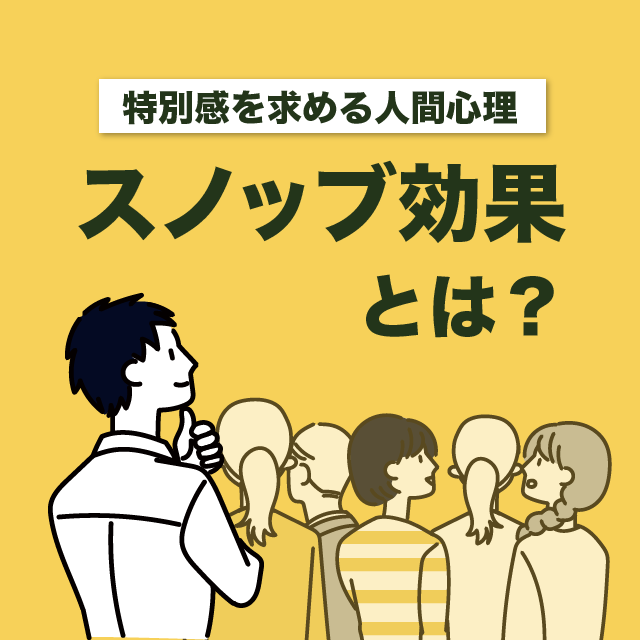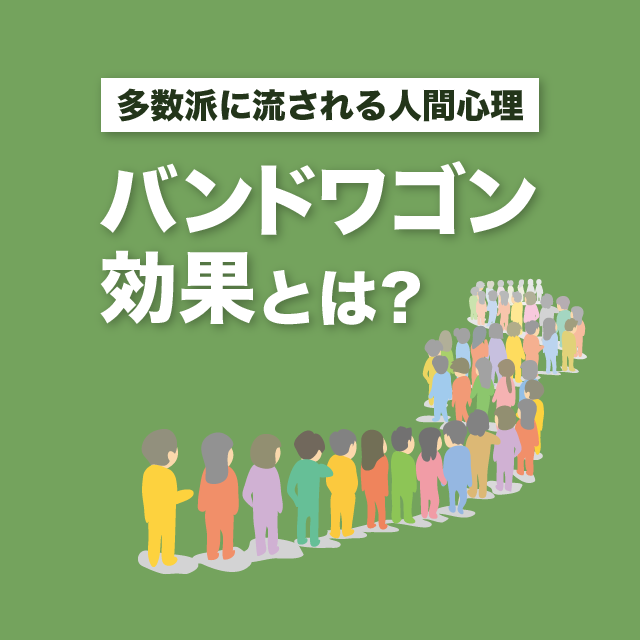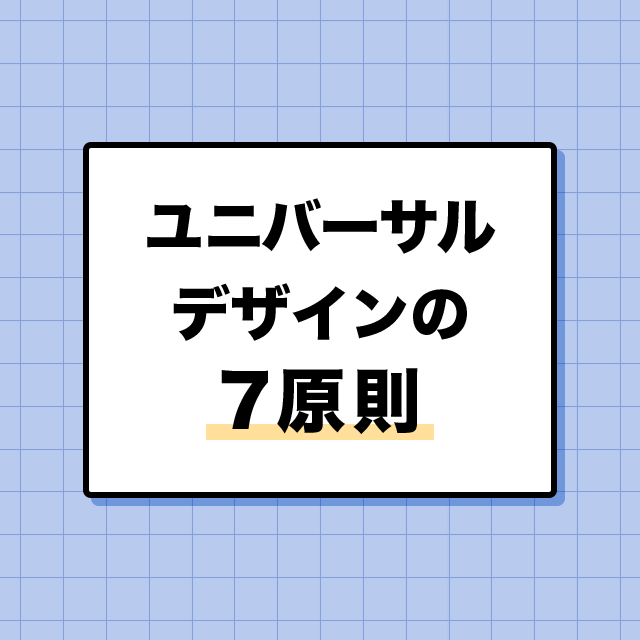色彩心理学とは
色彩心理学とは、色が人の感情や行動、思考にどのような影響を与えるかを研究する心理学のひとつです。私たちは日々さまざまな色に囲まれて生活していますが、単に色を認識しているだけではなく、無意識のうちに色から感情や印象を読み取り、判断や気分に影響を受けています。色の持つ性質を理解し活用することで、あらゆる分野で効果的な表現が可能になります。
色が与える4つの効果
1.心理的効果
色には、注意を引く、集中力を高める、落ち着かせるなど、人の思考や判断に働きかける力があります。たとえば、赤やオレンジなどの暖色系は興奮や緊張感を引き起こし、青や緑の寒色系は落ち着きや安心感をもたらします。こうした心理的な影響は、店舗の照明やパッケージデザインなどに応用されています。
2.生理的効果
色は人間の身体にも影響します。たとえば、赤を見ると心拍数や血圧が上昇しやすく、逆に青や緑は脈拍を安定させ、筋肉の緊張を和らげる効果があるとされています。これらの反応は、医療現場のカーテンや制服の色選び、スポーツウェアのデザインにも応用されています。
3.感情的効果
色は、喜びや怒り、悲しみといった感情を引き起こす効果も持っています。黄色は陽気さや希望を感じさせ、紫は神秘的な気分を生み出します。また、黒は威厳や不安、白は清らかさや孤独感などを引き起こすことがあります。このような感情喚起は、映像演出やブランドカラーの設定において重要な役割を果たします。
4.文化的効果
色の意味は、文化や社会的背景によって大きく異なる場合があります。たとえば、日本では白は「清潔」や「神聖」などのプラスのイメージが多いですが、海外では「病気」や「幽霊」など不吉なイメージを持つ国も多くあります。また、個人の経験や記憶、性格によっても色の受け取り方は変わるため、万人に同じ効果を与えるわけではありません。
色が与える一般的な心理的イメージ
赤
赤は、情熱や興奮、エネルギーといった活発な印象を与える一方で、危険や警戒も連想させます。このため、セールのPOPや飲食店の内装など、人の行動を促す場面でよく使われます。
青
青は、冷静さや誠実さ、信頼感といった印象を持ちます。人の緊張を和らげる効果があるため、銀行やIT企業、医療機関のロゴや制服などでよく見られます。
黄
黄色は明るく陽気な印象を持ち、気分を高めたり、目を引く効果があります。ただし、使いすぎると不安や緊張感を与えることもあるため、バランスに気をつけて使用することが重要です。
緑
緑は自然や調和、安全の象徴とされ、心身をリラックスさせる効果があります。目に優しく、長時間見ても疲れにくい特性があるため、環境デザインや医療現場、オーガニック商品のカラーとして適しています。
黒
黒は高級感や重厚さ、権威を感じさせます。ファッションやラグジュアリーブランドに多く用いられますが、場合によっては圧迫感やネガティブな印象を与えることもあります。
白
白は清潔さや純粋さ、無垢なイメージを持ちます。空間を広く見せる効果もあり、医療やブライダル、ミニマルデザインなどに多く用いられます。
まとめ
色彩心理学は、色が人に与える印象や感情の変化を分析し、意図的に活用するための知識です。色の持つ意味や影響を理解し、目的や状況に応じて使い分けることで、より効果的で説得力のある表現が可能になります。